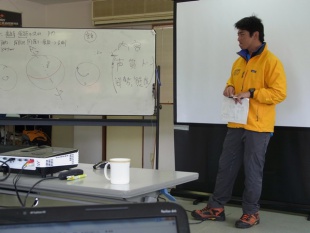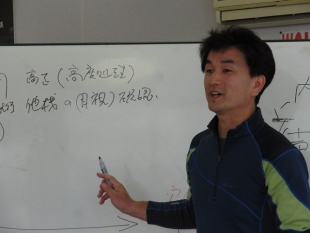パイロットセミナーin 平尾台 レポート:飛来 尚美(SSA平尾台パラグライダースクール)
「ソアリングを極める」をテーマに5月25日・26日SSA平尾台で開催されました。フライトは、初日一日だけでしたが満足の二日間でした。
25日
朝8時、目をキラキラさせながら期待に胸を膨らませたスクール生が集合。岡田氏より、ロールインさせる為のタイミングとブレーク操作などを聞きながらイメージトレーニングを重ねていきます。早々に山に上がり、講習生が次々とテイクオフしていきます。ガグリングには程遠い状態ですが、それでも満足そうな皆さんでした。
26日
この日は、風が強く机上講習となりました。昨日のフライトの反省とガーグリングへの入り方などを再確認。講習生からのリクエストで野外でのレクチャーとなりました。
けっして、踊っているのではありません。皆さん、真剣にガーグリングしているつもりです。
今回のセミナーでは、正しい旋回の必要性を勉強し、ルールを知った上で、譲り合いながら安全に飛ぶことが大切。相手が(もしくは、自分自身が)ルールを知らなかったら危険だということです。・・・「危険人物」にならないよう気をつけましょう。
主催:SSA平尾台パラグライダースクール
:エアハートパラグライダースクール
協力:岡田 直久(JPA教育事業部)
レポート:富重 薫(エアハートパラグライダースクール)
天気は快晴!しかし残念ながらフォローウィンドのため研修室での更新会となりました。
午前中は近年の事故についての傾向。ソロフライトにおいてもタンデムフライトでも確立された基礎技術の上で風の変化にあわせた操作の重要性を理解しました。また、機材の進化に関してインストラクターの知識・情報の更新も事故減少やフライヤーへのサービスに重要です。
午後は富士火災海上保険の山本氏によるJPA保険制度の説明を行い。内容、疑問点についての質疑応答を行いました。
インストラクターはフライヤーの皆さんにパラグライダーというスポーツを楽しんで頂くために正しい知識、情報に基づいた指導・情報提供が必要です。
機材が進化すれば、理論・技術も変わります。インストラクターも進化しパラグライダーの素晴らしさを伝えていきましょう。
会場:西部公民館(福岡県・平尾台)
講師:岡田 直久(JPA教育事業部)
山本 邦浩(富士火災海上保険)
パフォーマンスインストラクター更新
高木 弘志(JMB四国パラグライダースクール)
富重 薫(エアーハートパラグライダースクール)
インストラクター更新:
河辺 清治(トップアウトパラグライダースクール)
山口 博史(長崎フリーフライト)
山本 雅史(タートルズパラグライダースクール)
飛来 尚美(SSAスカイスポーツ振興会)
長島 信一
アシスタントインストラクター更新
赤尾 浩太郎(エアーハートパラグライダースクール)
浦郷 賢也(長崎フリーフライト)
協力:SSAスカイスポーツ振興会
エアーハートパラグライダースクール
今季最後となるリガー更新研修会が山形県白鷹で行われました。更新研修会を終えるたびに、これですべて伝えきったかなという思いがありますが、機材が変化し続ける以上そうもいかないようです。今回も最近の傾向と対策の講習からスタート。様々な機材に対応できるかどうかは「モノ」の本質が見えているかどうかで決まります。型だけを暗記するだけでは、応用力や対応力は身に付きません。なぜそのような型になるかということを知る必要があります。
午前中は講習、デモンストレーションを通じてそのようなことを意識していきました。簡単に昼食を済ませ、午後はパッキング実技。それぞれハーネスを交換して、普段扱っていないハーネス、パラシュートのパッキングをし、応用力を高めることにしました。細部にもこだわり、1つのパッキングが終わるのに約2時間。数をこなすことではなく、とにかく「こだわる」ことで理解を深めていくことにしました。
集中力を切らさないように配慮しながら、予定数のパッキングを終了したのは17時過ぎ。2年に一度のリガー更新会を無事終えました。みなさん、お疲れ様でした。JPAには各スクール間の良いコミュニケショーンとネットワークがあります。それを最大限に活用し、疑問などがあればみんなで協力し解決していきましょう。
講師:植木 亨(トントンとんびパラグライダースクール)
更新:鈴木 考世(マップス)
立花 圭介(七時雨パラグライダースクール)
小野寺 久憲(寒風山パラグライダースクール)
協力:トントンとんびパラグライダースクール
雨も上がり爽やかな朝となりました。予定通り、宿題の講習実技から開始。順番に一人ずつ、教壇に立ち講習を行いました。講習は内容以上に「話し方」で受け手の印象は決まります。その「話し方」・・・態度、姿勢、声質、声の大きさが重要なファクターとなります。講義がどうだったか、みんなでその辺を含め話し合い、改善を図りました。午前中に一人2回ずつ講習実技、いい緊張感を味わったのではないでしょうか。
2時間目は「ハーネス」。これもインストラクターにとっては重要な科目です。ハーネス構造、調整、機能は確実に知っておく必要があります。この講義が終わるころから、空中にパラグライダーも見えだしたので私たちもすぐに準備をしテイクオフへ。旋回を意識しながら、みなさん30分ほどのフライト。終わったもちろんビデオ解析です。
最終日ということもあり、15時の終了を予定していましたが、科目をすべて消化できていません。引き続き、教室で講義を続行。最後の「パラシュート」の講義を終えたのは17時を回っていました。
検定会はこの秋を予定しています。みなさん、これから半年間、計画立てて練習、勉強をしていくことと思いますので、各スクールではご協力をお願いします。
それにしても3日間、充実した研修会となりました。次は検定会でお会いしましょう。
エリア、教室、宿泊所をご提供いただいたエアパークCOOのみなさま、ありがとうございました。
協力:エアパークCOOパラグライダースクール(茨城県)