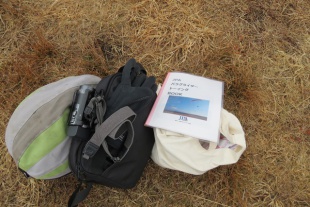宿泊場所も同じということで昨晩は遅くまでトーイングの話で盛り上がりました。
2日目開始。8時45分、ふもとっぱらに集合。まずは昨日の総括を再び行い、今日のテーマへと入りました。今日はタンデム、そして初心者の方を想定したソロフライトが課題。さっそく準備をすすめて、各自配置につきました。2日目ということもあり、みなさん手際良く、すぐに実技を行うことができました。
タンデムフライトとなると、昨日とは幾分イメージも違うようで最初は戸惑い気味でしたが、数本行ううちに的を得てきました。今日も各配置を交代しながら行い、すべてのポジションをマスターするように努めました。
お昼休みを挟んで、午後も実技を続行。トラブルを想定したトレーニングも行い、トーイングへの理解を深めました。
すべての実技科目を終えたのは16時前。2日間のトーアップ数は78本におよびました。すぐに片づけをして会場を朝霧パフォーマンスセンターに移し、口頭試問。講師陣からの質問にみなさん順番に答えていきます。最後に今回の総評を行い、みなさん日本初となるウインチオペレーター技能証を手にしました。みなさん新たなチャレンジに非常に新鮮な気持ちを得たようです。今後のみなさんの活躍に期待します。
会場:朝霧ふもとっぱら
富士山YMCA
アエロタクトパフォーマンスセンター
講師&協力:
小野寺 久憲(寒風山パラグライダースクール/JPA副会長)
真藤 正一(MKクラフト)
宮田 歩(アエロタクト)
*2日間の模様を収めたビデオを編集中です。
雨上がりの朝霧となりました。空気も入れ替わったようで、昨日の寒さも和らぎました。地面が乾くのを待ちながら、まずはアエロタクトパフォーマンスセンターをお借りして机上講習からスタートしました。まずは教本の内容を正しく理解することが、これから実技を行う上でも大切です。教本は80ページに及びますので、重要なポイントに的を絞り解説。イメージをある程度作ったところで、朝霧ふもとっぱらに移動です。
静穏のふもとっぱらはこれからトーイングを行うには最適なコンディションです。ウインチの取り扱いの説明を受け、デモンストレーションを見たところですぐにみなさんオペレーションの実技から開始です。ファーストインプレッションはみなさんそれぞれだったようですが、緊張感にあふれるインストラクターのみなさんの表情は印象的でした。一通り、オペレーションを体験したところで、パイロット、テイクオフアシスタント、トーラインの運搬の各パートを交代しながら実践です。どのパートも覚えることはいっぱい、教本を片手にみなさん奮闘です。朝早くからの研修で、昼過ぎには疲れもピークであったのではないかと思いますが、疲れている暇もないほど、次から次へ、パラグライダーがトーアップされていきます。活気あふれる研修は夕方までたっぷり行われ、ひとまず実技は終了です。
終了後は宿舎となるYMCAに移動。さっと食事を済ませ、机上講習。航空力学、バッテリーの取り扱い、トーイングスクールの運営・・・講師それぞれ得意分野の講義が夜遅くまで展開されました。
会場:朝霧ふもとっぱら
講師&協力:
小野寺 久憲(寒風山パラグライダースクール/JPA副会長)
真藤 正一(MKクラフト)
宮田 歩(アエロタクト)
インストラクター養成研修会延期のお知らせ
3/12-14に予定していましたインストラクター養成研修会ですが、都合により期日を延期した上で実施します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
新たな日程は 4月または5月を予定しています。参加の意志のある方は3月1日(金)までに事務局までご連絡ください。参加予定の方と日程を調整の上、開催日を決定します。
よろしくお願いします。
JPA教育事業部
JPAがスタートして10年が経ち、一つの目標である「事故防止」は、協会の取組み、各インストラクターの意識改革、そして全てのパイロットの方々のご協力のもと、減少方向に向かっていて、成果を上げていると言えると思います。しかし残念ながらまだ事故は起きています。これを限りなくゼロに向けるべくこれからの10年を進んで行く為には何ができるか?今回の更新研修会の準備は、ここから始まりました。
当日は冬型気圧配置の為、次第に風が強くなる可能性が高く、集まり次第早々にテイクオフに上がるが、既に強い風が吹いているコンディション、実技課目を意味のある内容にするには、空気が動き過ぎるのでフライトは中止し、すぐに室内へ移動して講義となりました。
まずは教育事業部の岡田氏より、基礎とは何か?我々インストラクターとして求めるべき方向、各自がさらに追求しなければならない物について、お話を頂きました。パラグライダーの技術の説明は、色々な方法や様々な言葉で行うことが可能となってしまいますが、これではより複雑になるだけでなく、エラーが発生し易い要因を増やしてしまう事になります。我々インストラクターはよりシンプルに、そして誰にでも分かり易い言葉で、複雑な3次元の動きの説明をすることが求められています。この為にはパラグライダーの基本をさらに追求し、より深い理解を求める努力が必要となります。このように、今回のテーマは基礎をより深く掘り下げて、理解を深めること。そして理解したことを、自分の言葉にして初めて人に伝える事ができる知識となること。そしてその知識の伝え方は相手によって様々であるので、色々な手法も必要になることでした。これらを共に話し合い追求するいい機会となりました。この機会をきっかけに、より深い理解を求めて行けたらと思います。
最後になりますが、自分が知らないということをまず知って、研究して得た知識をさらに検証を繰り返して知恵にすること。これを怠らないでこれからの10年に向けて進んで行けばより事故をゼロに近付けることができると信じて、やって行こうと講義を終了しました。